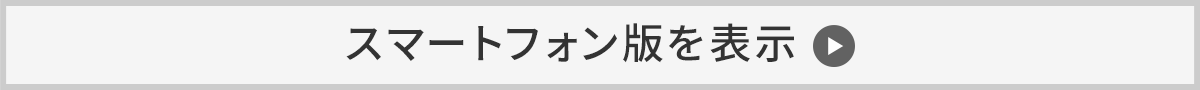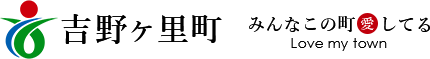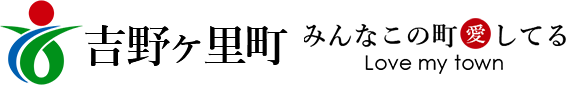吉野ヶ里町「いちばん!」

日本茶樹栽培発祥の地

日本最初の茶樹栽培地の記念碑
ビタミンCなどを多く含み、健康飲料水としても人気が高まっている緑茶。このお茶栽培発祥の地はここ吉野ヶ里町です。
1191年、臨済宗の開祖栄西禅師は宋(今の中国)留学から帰る際、霊仙寺に滞在し、宋から持ち帰った茶の種子を霊仙寺西の谷の石上(いわかみ)坊の庭にまき、茶を栽培し、その製法をもたらしました。これが、「日本最初の茶樹栽培地」であるといわれるところです。
江戸時代後期の資料によれば、当時霊仙寺一帯には9反5畝(約1ヘクタール)の茶園があったとされ、今では往時を偲ぶ唯一の建物乙護法堂前にその一部が残っており、地元坂本地区の皆さんが管理しています。
今では山すそ一面に広がる緑の茶畑は、八百年の歴史を物語っています。
また、お茶に関して古い歴史をもつ中国の湖北省から、「茶聖」陸羽の研究グループ一行が視察に訪れるなど、吉野ヶ里町で茶道を通じた日中両国の友好が深まつています。

霊仙寺跡からの眺望

中国からの視察団
.gif)
吉野ヶ里遺跡

推定延長2.5キロメートルの壕に囲まれた、全国一の規模を誇る環壕集落跡。3,000基を超えるかめ棺や墳丘墓などが発掘されました。墳丘墓からは有柄(ゆうへい)銅剣やガラス製の管玉(くだたま)なども出土しています。
把頭飾付き有柄細形銅剣

朱塗りのかめ棺からガラス製菅玉79個とともに発見。一般人のかめ棺からは銅剣やガラス製菅玉は出土しておらず、特権階級の墓だということが分かります。出土状況が明らかで学術的価値も高く、銅剣の出土は国内で4番目。
ガラス製管玉
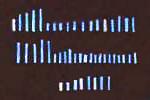
被葬者の身分を表すと考えられる副葬品の一つで、朱塗りのかめ棺から79個発見されました。銅剣とともに、大陸との交流を証明するものです。
巴形銅器

盾の飾り金具や魔除け、まじないに使われていたといわれる巴形銅器。鋳型片の出土は国内で初めて。吉野ヶ里は弥生時代の最先端の鋳造技術を持っていたハイテク都市であったことが分かります。
物見やぐら
「魏志倭人伝」に記された楼観(ろうかん)跡と推定される、弥生時代の見張り台。吉野ヶ里遺跡は小さな集落・ムラを統括していた中核集落・クニと推測されており、物見やぐらで侵略者を監視していました。
竪穴住居
2本の柱で支えられた弥生時代後期の長方形の住居跡。炉(ろ)跡やベッド状遺構も復元。床より一段高くなっただけのベッド状遺構が弥生人のベッド。そこで寝ていたと考えられています。
高床倉庫
床を高くし、風通しを良くした倉庫。吉野ヶ里遺跡からは、通常の弥生時代の倉庫より大きな6本柱の大規模な高床倉庫が21基発見されました。大人が4〜5人は入れる大きさです。
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0350
ファックス:0952-53-1106
メールフォームによるお問い合わせ