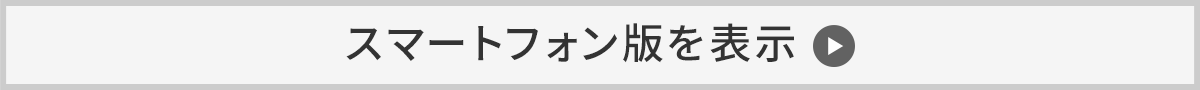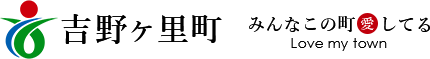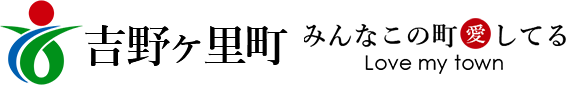【調整給付金の受取りには申請が必要です 提出期限 令和6年11月29日】定額減税しきれないと見込まれる方へお知らせ
令和6年分所得税および令和6年度個人住民税で実施される定額減税において、 定額減税を十分に受けられない(減税しきれない)と見込まれる方に対し、差額を調整して給付します。
「調整給付金」とは
令和6年度税制改正により、納税者および同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われます。(注1)
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。(注2)

(注1)定額減税の詳細は、国税庁や総務省ホームページ、町ホームページ(「令和6年度個人住民税の定額減税について」)をご覧ください。
(注2)令和5年中の所得に対する課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税市区町村より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合等には、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、「所得税の定額減税不足分」と「個人住民税の定額減税不足分」の合計値を1万円単位で切り上げた額を支給します。
支給対象
吉野ヶ里町の定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(注4)」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
(注4) 令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、早急に給付を行うため、令和5年分の所得・扶養親族等の情報をもとに、国が提供する算定ツールを利用して令和6年分の推計所得税額を算定しています。
※個人情報保護の観点から、個別のお問い合わせ(ご自身や家族が支給対象かどうか・給付金額など)には回答することができません。あらかじめご了承ください。
支給金額
金額の算定方法
次の(1)と(2)の合計を1万円単位で切り上げた額。
(1)所得税分で定額減税しきれない額=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税分で定額減税しきれない額=個人住民税分定額減税可能額-令和6年度個人住民税所得割額
支給金額の具体例
【計算例】ケース1:納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
(算出条件)
・4人家族(本人、妻、高校生1人、中学生1人)
・納税者本人の給与収入2,716,000円(給与所得1,821,200円)
・納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前) 8,650円
・納税者本人の個人住民税所得割額 1,100円
(調整給付額)
1.所得税分控除不足額
定額減税可能額:120,000円−令和6年分推計所得税額(減税前):8,650円=111,350円
2.住民税分控除不足額
定額減税可能額:40,000円−令和6年度個人住民税所得割額(減税前):1,100円=38,900円
調整給付額(1.所得税分控除不足額+2.住民税分控除不足額)
111,350円+38,900円=150,250円
支給額は160,000円(1万円単位で切上げ)となります。
【計算例】ケース2:納税義務者本人が妻を扶養している場合(65歳以上年金受給者)
(算出条件)
・2人家族(本人、妻)
・納税者本人の給与収入2,898,185円(年金所得1,798,185円)
・妻の年金収入736,355円(年金所得0円)・・・所得税および住民税は非課税
・納税者本人の令和6年分推計所得税額(減税前) 25,150円
・納税者本人の個人住民税所得割額 55,200円
(調整給付額)
1.所得税分控除不足額
定額減税可能額:60,000円−令和6年分推計所得税額(減税前):25,150円=34,850円
2.住民税分控除不足額
定額減税可能額:20,000円−令和6年度個人住民税所得割額(減税前):55,200円=−35,200円
定額減税可能額<住民税所得割額のため、不足額0円
調整給付額(1.所得税分控除不足額+2.住民税分控除不足額)
34,850円+0円=34,850円
支給額は40,000円(1万円単位で切上げ)となります。
手続き方法
- 本町で令和6年度個人住民税が課税されている対象者には、9月中旬に「調整給付金支給確認書」をお届けします。
- 記載例を参考に記入いただき、同封の返信用封筒で返送してください。
- 返送期限は、令和6年11月29日(消印有効)までです。
※期限内に返送されない場合は、給付金を辞退したものとみなします。
※記入漏れがある場合は、問い合わせ・再返送等を含め振込に日数を要します。
支給の時期
確認書の返送があった日から4週間後を目安に支給します。
※申請が集中した場合は、上記より遅れる場合があります。
Q&A
私は定額減税・調整給付の対象ですか。
定額減税の対象となる方は、特別徴収税額の決定・変更通知書または納税通知書に定額減税の金額を記載していますので、ご確認ください。
調整給付の対象となる方には、9月中旬に「調整給付金支給確認書」をお届けします。
所得税と個人住民税所得割のいずれか一方のみが課税になっている場合は、どのようになりますか。
いずれか一方のみが課税で、定額減税の対象となっている場合は、調整給付は税額がない税目分も控除不足額を算出し、減税対象人数1人につき4万円(3万円+1万円)を基礎として給付の対象となります。
所得税も個人住民税所得割額もどちらも非課税の場合は、どのようになりますか。
所得税も個人住民税所得割もどちらも非課税の場合は、調整給付の対象となりません。
私はどの自治体から定額減税・調整給付が受けられるのですか。
個人住民税の定額減税および調整給付を実施するのは、令和6年度分個人住民税を課税している自治体です。個人住民税は、原則としてその年の1月1日において市区町村内に住所を有する個人に対して課税を行っていますので、必ずしも現在の住民票上の自治体とは限りません。また、所得税の定額減税については国税庁が実施しています。
住宅ローンやふるさと納税などの税額控除を受けている場合、調整給付は支給されますか。
税額控除適用後の個人住民税所得割額や所得税額から定額減税を実施しますが、そこで減税しきれない分があった場合に調整給付を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
メールフォームによるお問い合わせ